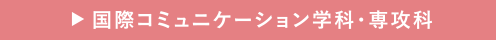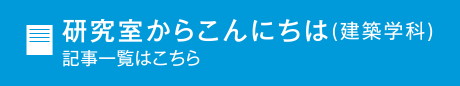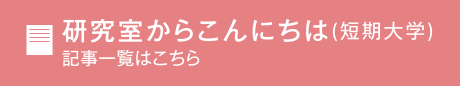コンピュータ・サイエンスをご存じですか?(国際コミュニケーション学科 藤戸敏弘)
研究室からこんにちは(短期大学)
昨年は、自分の専門分野からアルゴリズムについてお話しさせていただきましたが、それにしても昨今のAIブームは連日メディアで取り上げられ凄まじいですね。過去にもAIがブームになったことはあり、現在は第3次のブームにあるようです。第1次の時は昔過ぎてまったく記憶にないのですが、80年代の第2次ブームの際は日本経済も絶好調で、まだ個人ではパソコンすら簡単に所有できない時代でしたが、第五世代コンピュータという人工知能コンピュータの開発を目指す国家プロジェクトで大いに盛り上がっていたことを覚えています。その第2次AIブームも90年代には終焉を迎えるわけですが、その際AIの限界として挙げられたことの一つが、コンピュータに常識を身につけさせる困難さだったように記憶しています。人間でさえ何年もかけてようやく身につけられるものを、如何にコンピュータに植え付けるか、ということだったかと思いますが、今やGoogleなどが構築している巨大データベースを考えれば、そのような障壁も易々と乗り越えられそうです(それどころか、知識量に関しては、もはや誰もネットに繋がったコンピュータに敵わないですよね)。更に最近話題になったのがノーベル賞の受賞者です。というのも、2024年度の物理学賞はJohn J. Hopfield氏とGeoffrey E. Hinton氏に、化学賞はDavid Baker氏、Demis Hassabis氏、John M. Jumper氏に授与されたのですが、物理学賞の2名はいわゆるAIの基礎、そして化学賞のHassabis氏とJumper氏はAIの応用の研究者と考えられているからです。
このように、何もかもがAIによって我々の社会・生活が塗り替えられそうな勢いですが、皆さんは「AIの父」と呼ばれる人物をご存知でしょうか?最近は前出のHinton氏がそう呼ばれているようですが、従来は(そして今も)英国の数学者Alan Turingを指していました。その波乱万丈に満ちた生涯は映画『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』の他、戯曲、伝記、小説等にも描かれていますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。第二次世界大戦中、ナチのエニグマという当時解読不能と目されていた暗号機による暗号文の解読に貢献したものの、1952年同性愛による逮捕・有罪を受け、その2年後には亡くなっています(自殺と目されている)。幸い、その後英国ではTuringの名誉は回復され、肖像画が50ポンド紙幣に採用されたりしています。

Turingは今日チューリングテストとして知られている実験を提案し、人工知能の問題を提起するなどの功績から「AIの父」と呼ばれるようになったのですが、それ以外にも極めて重要な業績を残しています。大戦前に「チューリングマシン」という計算モデルを提示し、その後の電子計算機の開発につながる貴重なアイデアを提供したり、ある具体的問題が計算不可能である(計算できない=解き方を構成できない、つまりアルゴリズムが存在しない)ことを証明しています。それ故、彼は「コンピュータ・サイエンスの父」とも呼ばれているのです。
ようやく、タイトルにある「コンピュータ・サイエンス」が出てきました。日本語では,直訳すると「計算機科学」、「コンピュータ科学」になりますが、ほぼ同義の情報工学や情報科学がよく使われます(ちなみに、計算科学=computational scienceという似て非なる分野も存在します)。そもそも"computer science"という呼び名は1960年代に数値解析アナリストにより付けられたようですが、そのせいか、「計算機の科学」と受け取られそうな名前になっています。しかし、Wikipedia(英語版)に”Computer science is the study of computation, information, and automation.”と書かれているように、「計算機」に限らずより広く「計算や情報の科学」を意味し、前回お話ししたアルゴリズムなどの基礎理論から計算機のハードウエア・ソフトウエア,そしてAIやコンピュータ・グラフィックスといった計算機の応用までを含む領域を表します。特にscienceとあることから、自然科学における伝統的な数学、物理学、化学、生物学などとは異なる「新しい科学」という意味が込められているのではと思います。コンピュータ・サイエンス分野における世界最大の学会がAssociation for Computing Machinery (ACM)で、ACMが毎年授与するチューリングの名を冠した「チューリング賞」は、コンピュータ・サイエンス分野での最高の栄誉とされています(前出のHinton氏も2018年に受賞)。ノーベル賞には数学同様、コンピュータ・サイエンスの分野はありませんので、今回4名ものコンピュータ・サイエンス(AI)の研究者が受賞したことは驚きでした。
1930年代に「計算とは何か?」を追求するチューリングらの研究を源流とし、世の中のあらゆる現象(自然現象を含めて)を計算として捉え、計算で説明することを目指す、そのようなサイエンス、それがコンピュータ・サイエンスなのです。
このように、何もかもがAIによって我々の社会・生活が塗り替えられそうな勢いですが、皆さんは「AIの父」と呼ばれる人物をご存知でしょうか?最近は前出のHinton氏がそう呼ばれているようですが、従来は(そして今も)英国の数学者Alan Turingを指していました。その波乱万丈に満ちた生涯は映画『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』の他、戯曲、伝記、小説等にも描かれていますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。第二次世界大戦中、ナチのエニグマという当時解読不能と目されていた暗号機による暗号文の解読に貢献したものの、1952年同性愛による逮捕・有罪を受け、その2年後には亡くなっています(自殺と目されている)。幸い、その後英国ではTuringの名誉は回復され、肖像画が50ポンド紙幣に採用されたりしています。

Turingは今日チューリングテストとして知られている実験を提案し、人工知能の問題を提起するなどの功績から「AIの父」と呼ばれるようになったのですが、それ以外にも極めて重要な業績を残しています。大戦前に「チューリングマシン」という計算モデルを提示し、その後の電子計算機の開発につながる貴重なアイデアを提供したり、ある具体的問題が計算不可能である(計算できない=解き方を構成できない、つまりアルゴリズムが存在しない)ことを証明しています。それ故、彼は「コンピュータ・サイエンスの父」とも呼ばれているのです。
ようやく、タイトルにある「コンピュータ・サイエンス」が出てきました。日本語では,直訳すると「計算機科学」、「コンピュータ科学」になりますが、ほぼ同義の情報工学や情報科学がよく使われます(ちなみに、計算科学=computational scienceという似て非なる分野も存在します)。そもそも"computer science"という呼び名は1960年代に数値解析アナリストにより付けられたようですが、そのせいか、「計算機の科学」と受け取られそうな名前になっています。しかし、Wikipedia(英語版)に”Computer science is the study of computation, information, and automation.”と書かれているように、「計算機」に限らずより広く「計算や情報の科学」を意味し、前回お話ししたアルゴリズムなどの基礎理論から計算機のハードウエア・ソフトウエア,そしてAIやコンピュータ・グラフィックスといった計算機の応用までを含む領域を表します。特にscienceとあることから、自然科学における伝統的な数学、物理学、化学、生物学などとは異なる「新しい科学」という意味が込められているのではと思います。コンピュータ・サイエンス分野における世界最大の学会がAssociation for Computing Machinery (ACM)で、ACMが毎年授与するチューリングの名を冠した「チューリング賞」は、コンピュータ・サイエンス分野での最高の栄誉とされています(前出のHinton氏も2018年に受賞)。ノーベル賞には数学同様、コンピュータ・サイエンスの分野はありませんので、今回4名ものコンピュータ・サイエンス(AI)の研究者が受賞したことは驚きでした。
1930年代に「計算とは何か?」を追求するチューリングらの研究を源流とし、世の中のあらゆる現象(自然現象を含めて)を計算として捉え、計算で説明することを目指す、そのようなサイエンス、それがコンピュータ・サイエンスなのです。