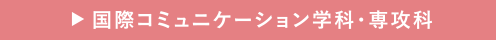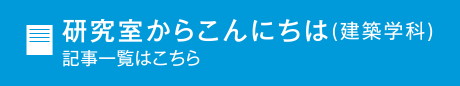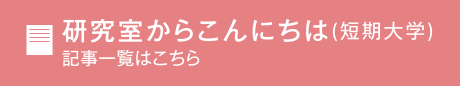2025年10月号「研究室からこんにちは」(寺澤 陽美)ハロウィン:その歴史と風習から商業イベントへ
研究室からこんにちは(短期大学)
ようやく暑い夏が過ぎ、秋を感じる季節となりました。まもなく、日本でもすっかりおなじみになったこの時期ならではのイベント、ハロウィン(Halloween)がやってきます。
ハロウィンは、現在では日本をはじめ世界各地で親しまれている季節のイベントの一つですが、その歴史を調べてみると、古くて興味深いものです。

ハロウィンシーズンのカボチャの装飾
ハロウィンはもともと、ケルト民族の風習と深くかかわっており、その起源は2000年以上前というから驚きです。
現在でいうアイルランドなどに住んでいた古代ケルト人の、サムハインまたはサウィン(Samhain)という新年の祝祭にさかのぼります。
新年の祝祭では、装束を身につけた人々はかがり火を焚き、彷徨う霊を払い、収穫を祝うなどしていました。
新年の前日となる10月31日は、この世とあの世の距離が最も近くなり、行き来ができる日と考えられていました。
この日には死者の霊が家族のもとを訪ねてきたり悪霊が一緒についてきたりすると信じられていたことから、人々は仮装して身を護ったり火を焚いて悪霊を遠ざけたりする風習がありました。
これがもととなり、やがてハロウィンの時期に仮装する文化となったとされています。
ハロウィンという名前は、11月1日のカトリックの「諸聖人の日(万聖節)」の古い呼び方に由来します。
諸聖人の日の旧称の一つであるAll Hallowsという言葉に、前夜を意味するeveが加わってHallowseveとなり、その後変化してHalloween(ハロウィン)という呼び方が定着しました。

住宅の庭や玄関前のハロウィンの装飾

ハロウィンのジャック・オー・ランタン
ハロウィンは、アイルランド、ヨーロッパ各地で広がり、20世紀前半までにアメリカ諸都市へと伝わりました。
現在アメリカでは、子どもたちが仮装して近所を回り、お菓子をもらうイベントとして親しまれています。
日本では、1970年代、老舗玩具店として知られるキディランド原宿店が、欧米風文化の紹介と普及を目的に取り扱ったことをきっかけに、季節のイベントとして全国へ広がることとなりました。
現在では、テーマパークでのハロウィンイベントに参加したり繁華街などに仮装して繰り出したりするのが、この時期ならではの家族や友人との楽しみ方として広く認知されています。
一方で、ハロウィンの週末の大混雑やごみ問題、一部の人の悪乗りやトラブルが社会問題として取り上げられることもあり、渋谷や名古屋など一部地域や施設では、ハロウィンの週末の交通や出入りを規制する動きもあります。

仮装する人々で大混雑の渋谷
ここまで、ハロウィンの起源とイベント化した習慣について、まとめました。
最後に、ハロウィンにまつわる英語表現をいくつかご紹介します。
Jack-o'-Lantern(ジャック・オー・ランタン):「ジャックの提灯」の意味で、元々はカブを、現在ではカボチャを使って目・口・鼻をくり抜いて顔の形に見立てたもので、ハロウィンの代表的な装飾として知られています。
Trick or Treat(トリック・オア・トリート):「いたずらかごちそうか」「もてなしを、でなければいたずらするぞ」という意味で、ハロウィンの夜に、お化けや精霊に仮装した子どもたちが近所の家々を回り、玄関先でこのように言います。
Happy Halloween(ハッピー・ハロウィン):近所の子供たちの訪問を受けお菓子をねだられた各家庭では、このような言い回しで応じ、キャンディやチョコレートなど用意したお菓子を渡します。
ハロウィンのイベントに参加する人もそうでない人も、街でハロウィンの装飾や仮装して歩く人々を見かけることがあるでしょう。
そんな時、ちょっとその背景に思いを馳せながら、年に一度のイベントを楽しんでみてくださいね。
***************************
参考資料:
久松英二,佐野東生(2017)『多文化時代の宗教論入門』ミネルヴァ書房
リサ・モートン(2014)『ハロウィーンの文化誌』原書房
写真:ハロウィンのジャック・オー・ランタン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kobe_Mosaic17s3072.jpg
ハロウィンは、現在では日本をはじめ世界各地で親しまれている季節のイベントの一つですが、その歴史を調べてみると、古くて興味深いものです。

ハロウィンシーズンのカボチャの装飾
ハロウィンはもともと、ケルト民族の風習と深くかかわっており、その起源は2000年以上前というから驚きです。
現在でいうアイルランドなどに住んでいた古代ケルト人の、サムハインまたはサウィン(Samhain)という新年の祝祭にさかのぼります。
新年の祝祭では、装束を身につけた人々はかがり火を焚き、彷徨う霊を払い、収穫を祝うなどしていました。
新年の前日となる10月31日は、この世とあの世の距離が最も近くなり、行き来ができる日と考えられていました。
この日には死者の霊が家族のもとを訪ねてきたり悪霊が一緒についてきたりすると信じられていたことから、人々は仮装して身を護ったり火を焚いて悪霊を遠ざけたりする風習がありました。
これがもととなり、やがてハロウィンの時期に仮装する文化となったとされています。
ハロウィンという名前は、11月1日のカトリックの「諸聖人の日(万聖節)」の古い呼び方に由来します。
諸聖人の日の旧称の一つであるAll Hallowsという言葉に、前夜を意味するeveが加わってHallowseveとなり、その後変化してHalloween(ハロウィン)という呼び方が定着しました。

住宅の庭や玄関前のハロウィンの装飾

ハロウィンのジャック・オー・ランタン
ハロウィンは、アイルランド、ヨーロッパ各地で広がり、20世紀前半までにアメリカ諸都市へと伝わりました。
現在アメリカでは、子どもたちが仮装して近所を回り、お菓子をもらうイベントとして親しまれています。
日本では、1970年代、老舗玩具店として知られるキディランド原宿店が、欧米風文化の紹介と普及を目的に取り扱ったことをきっかけに、季節のイベントとして全国へ広がることとなりました。
現在では、テーマパークでのハロウィンイベントに参加したり繁華街などに仮装して繰り出したりするのが、この時期ならではの家族や友人との楽しみ方として広く認知されています。
一方で、ハロウィンの週末の大混雑やごみ問題、一部の人の悪乗りやトラブルが社会問題として取り上げられることもあり、渋谷や名古屋など一部地域や施設では、ハロウィンの週末の交通や出入りを規制する動きもあります。

仮装する人々で大混雑の渋谷
ここまで、ハロウィンの起源とイベント化した習慣について、まとめました。
最後に、ハロウィンにまつわる英語表現をいくつかご紹介します。
Jack-o'-Lantern(ジャック・オー・ランタン):「ジャックの提灯」の意味で、元々はカブを、現在ではカボチャを使って目・口・鼻をくり抜いて顔の形に見立てたもので、ハロウィンの代表的な装飾として知られています。
Trick or Treat(トリック・オア・トリート):「いたずらかごちそうか」「もてなしを、でなければいたずらするぞ」という意味で、ハロウィンの夜に、お化けや精霊に仮装した子どもたちが近所の家々を回り、玄関先でこのように言います。
Happy Halloween(ハッピー・ハロウィン):近所の子供たちの訪問を受けお菓子をねだられた各家庭では、このような言い回しで応じ、キャンディやチョコレートなど用意したお菓子を渡します。
ハロウィンのイベントに参加する人もそうでない人も、街でハロウィンの装飾や仮装して歩く人々を見かけることがあるでしょう。
そんな時、ちょっとその背景に思いを馳せながら、年に一度のイベントを楽しんでみてくださいね。
***************************
参考資料:
久松英二,佐野東生(2017)『多文化時代の宗教論入門』ミネルヴァ書房
リサ・モートン(2014)『ハロウィーンの文化誌』原書房
写真:ハロウィンのジャック・オー・ランタン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kobe_Mosaic17s3072.jpg