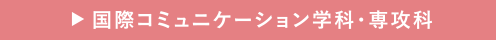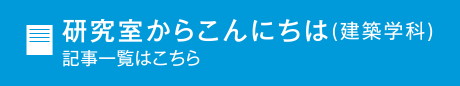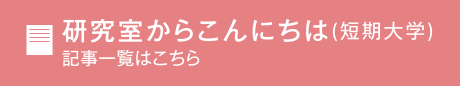新刊案内:『哲学者の「考え方」のツボがわかる西洋哲学講義』三苫 民雄 (著)
研究室からこんにちは(短期大学)
このたび拙著を出版いたしましたので、この場をお借りして紹介させていただきます。タイトルにあるように大学での哲学講義をイメージした本です。通信教育部だけでなく、通学部での教科書としても使えるように15回の講義を設けていますが、何よりも哲学を履修しない一般読者のみなさんにも読みやすいものとなるように留意しました。
本書の特徴は編集部がAmazon.comのサイトなどに次のようにまとめてくれています。
哲学者自身の言葉に触れつつ、彼らの「考え方」を解きほぐしながら、西洋哲学の思考の軌跡をたどる一冊。一般に「哲学は難しい」という印象がありますが、実際、哲学書を読んでみると、何を言いたいのかよくわからない文章にぶつかることがあります。その理由は、哲学独特の概念や用語、そして日本人とは異なる世界観(神)です。逆に、この二つの問題をクリアすれば、哲学者が問題としたことや言いたいことも見えてきます。そこで本書では、哲学者自身のテキスト(原文翻訳)を引用し、わかりにくい原文には「超訳」を付すことによって、哲学者の言わんとすることを平易にあぶり出します。さらに哲学者の「考え方=哲学者のアタマの中」を解説し、その思考の「核」に迫ります。単に要約された概説を受け身で読むのではなく、原文に触れることによって、直接、哲学者の考え方を共有することを目指します。哲学者の考え方の大事なところを、語り口調かつ“フツーの言葉”でわかりやすく解説した「哲学者たちの思考をたどる西洋哲学入門」です。
本書の特徴は翻訳ではありますが、哲学者自身の著作とその「超訳」を提示しているところかと思います。哲学の概論や哲学思想史の本は著者の解釈を中心に述べられているものが多く、元の哲学者がどのように書いているのかというところが必ずしも示されていません。そのため哲学の概説書の多くは読者にとっては、哲学者たちがどんなことを書いたかというよりは、哲学者たちの思想に対する著者のまとめを読まされているようなことになりがちです。また、しばしばその記述が百科事典を参照したような一般的な解説にとどまることがあり、私自身若い頃からこの点に不満を持つ一人でした。哲学は概説書よりは直接その思想家たちの書いたものを読まなければ始まらないと思っていましたので、本書ではすべて哲学者たちの著作からの一節が引用されています。引用元は現在入手可能な翻訳書から選んであります。
それに加えて哲学者の難解な表現がつまるところ何を言っているのかをはっきりさせるために「超訳」を施すというのも、本書の特徴をなしています。この超訳は当初難解な引用箇所だけにとどめていたのですが、引用文のほとんどすべてにこれを付すようにしたのは編集者のアイデアです。これによって本書は一層理解しやすくなったのではないかと思います。
なお、本書ではソクラテスから始めて代表的な哲学者を取り上げていますが、20世紀はハイデガー、ウィトゲンシュタイン、マイケル・ポランニーまでしか取り上げていません。そこで洋の東西を問わず現代の哲学者たちを中心に、生と死、他者、社会、来世、創造性といった問題を扱う続編を現在構想中です。乞うご期待。いやその前にどうぞAmazonでポチりとしてやってください。Kindle版も出ています。
新刊案内:『哲学者の「考え方」のツボがわかる西洋哲学講義』– 2025/2/20 ベレ出版 三苫 民雄 (著)
https://www.amazon.co.jp/dp/4860647858
本書の特徴は編集部がAmazon.comのサイトなどに次のようにまとめてくれています。
哲学者自身の言葉に触れつつ、彼らの「考え方」を解きほぐしながら、西洋哲学の思考の軌跡をたどる一冊。一般に「哲学は難しい」という印象がありますが、実際、哲学書を読んでみると、何を言いたいのかよくわからない文章にぶつかることがあります。その理由は、哲学独特の概念や用語、そして日本人とは異なる世界観(神)です。逆に、この二つの問題をクリアすれば、哲学者が問題としたことや言いたいことも見えてきます。そこで本書では、哲学者自身のテキスト(原文翻訳)を引用し、わかりにくい原文には「超訳」を付すことによって、哲学者の言わんとすることを平易にあぶり出します。さらに哲学者の「考え方=哲学者のアタマの中」を解説し、その思考の「核」に迫ります。単に要約された概説を受け身で読むのではなく、原文に触れることによって、直接、哲学者の考え方を共有することを目指します。哲学者の考え方の大事なところを、語り口調かつ“フツーの言葉”でわかりやすく解説した「哲学者たちの思考をたどる西洋哲学入門」です。
本書の特徴は翻訳ではありますが、哲学者自身の著作とその「超訳」を提示しているところかと思います。哲学の概論や哲学思想史の本は著者の解釈を中心に述べられているものが多く、元の哲学者がどのように書いているのかというところが必ずしも示されていません。そのため哲学の概説書の多くは読者にとっては、哲学者たちがどんなことを書いたかというよりは、哲学者たちの思想に対する著者のまとめを読まされているようなことになりがちです。また、しばしばその記述が百科事典を参照したような一般的な解説にとどまることがあり、私自身若い頃からこの点に不満を持つ一人でした。哲学は概説書よりは直接その思想家たちの書いたものを読まなければ始まらないと思っていましたので、本書ではすべて哲学者たちの著作からの一節が引用されています。引用元は現在入手可能な翻訳書から選んであります。
それに加えて哲学者の難解な表現がつまるところ何を言っているのかをはっきりさせるために「超訳」を施すというのも、本書の特徴をなしています。この超訳は当初難解な引用箇所だけにとどめていたのですが、引用文のほとんどすべてにこれを付すようにしたのは編集者のアイデアです。これによって本書は一層理解しやすくなったのではないかと思います。
なお、本書ではソクラテスから始めて代表的な哲学者を取り上げていますが、20世紀はハイデガー、ウィトゲンシュタイン、マイケル・ポランニーまでしか取り上げていません。そこで洋の東西を問わず現代の哲学者たちを中心に、生と死、他者、社会、来世、創造性といった問題を扱う続編を現在構想中です。乞うご期待。いやその前にどうぞAmazonでポチりとしてやってください。Kindle版も出ています。
新刊案内:『哲学者の「考え方」のツボがわかる西洋哲学講義』– 2025/2/20 ベレ出版 三苫 民雄 (著)
https://www.amazon.co.jp/dp/4860647858