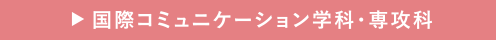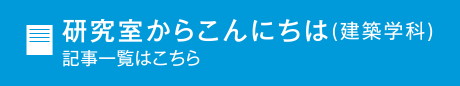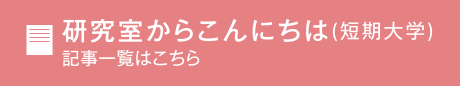なぜ動詞のing形には名詞的意味と動詞的意味が混在しているのか?(国際コミュニケーション学科 西田)
研究室からこんにちは(短期大学)
なぜ動詞のing形には、「~している: running、~する: surprising」という動詞的意味(現在分詞)と、「~すること」という名詞的意味(動名詞)の全く異なる意味と用法が混在しているのだろうか。さらに、動名詞に「~したこと、~していること」と過去的意味や進行的意味が含まれているのはなぜだろうか。I remember seeing you yesterday.(昨日あなたに会ったことを覚えている。(It is)nice meeting you.(あなたに会ったこと/会っていることは嬉しい。→ これからもずっとよろしく。長く話し込んだ後に述べる挨拶の言葉)。動名詞は、過去的、一般的、消極的、であるのに対して、to不定詞は、未来的、個人的、肯定的、であるという違いはどうして起こるのか。I remember to see you tomorrow. (明日あなたに会うことを覚えている。)(It is)nice to meet you.(あなたにこれから会うことが嬉しい。→ これからよろしく。初めに述べる挨拶の言葉)。
動名詞が多様な意味体系を持っている理由を説明するのに有力な論を、伊関(2013)は動名詞と現在分詞の歴史的変遷説に基づいて、次のように述べている:
1.古英語(450~1150頃)では V-ing(動名詞)と V-ende(現在分詞)があった。
2.古英語における動名詞 V-ing は現代のそれとは大きく異なる。古英語における V-ingの特徴は現代英語における「派生名詞」とほぼ同等の性質を持っていた。
(a) John’s“refusing”the offer suddenly surprised us.(動名詞:現代英語)
※古英語においては、動名詞は直接目的語を取らなかったが、現代英語では取る。
= (b) John’s sudden“refusal”of the offer surprised us. (派生名詞:現代英語)
古英語における動名詞 V-ing は (b) の派生名詞と同様に直接目的語を取らず、副詞と共起できない名詞的な文法構造を持っていた。一方、(a) のような現代英語における動名詞 V-ing は本来、現在分詞が持つ動詞的性質に近いものである。中尾・児馬編(1990, pp. 187-188)および児馬(1996, pp. 104-108)では、以下のように説明されている。

[iŋg](ingの発音)>[in]という動名詞の音的変化と、[ind](endeの発音)>[in]という現在分詞の音的変化によって両者がほぼ同音になり、現在分詞が[iŋg]とう音とingという形態を動名詞から譲り受け、一方、動名詞は動詞句の内部構造を持つ現在分詞の統語的性質(現在分詞語尾–ende は、–ing に変わる前から、of なしで、直接、対格目的語を従えていた)を譲り受けた。対格とは直接目的語(~を)を表す言葉である。同じ語尾を持つ、現代英語の動名詞と現在分詞は、古英語の動名詞と現在分詞が、それぞれの属性の一部を交換し合った結果、生まれた現象と見なすことができる(児馬1996, p. 109)。
to不定詞のtoは「~へ」という方向を表す前置詞のtoと同じ源から発している(大津 2004)。そこで、名詞的意味(~すること)を表すto不定詞と動名詞において、to不定詞が未来志向であるのに対し、動名詞は過去志向を表す傾向が生まれるのは必然の棲み分けである。現在を表すには、to不定詞も動名詞も同様に使用されるが、動名詞には現在分詞の持つ動詞的意味「~している、~する」も含まれているので、現在志向を表す場合には動名詞が多く使用されると考えられる。(It is)nice meeting you.(会ったこと/会っていることは嬉しい。→ これからもずっとよろしく。長く話し込んだ後に述べる挨拶の言葉)
動名詞は13~14世紀に本来持っていた名詞的性質に加え、動詞的性質を持っていた現在分詞との綴りと発音の統一により、現在分詞の持っていた動詞的意味を獲得した。その為、現代英語の動名詞には古英語からの名詞的意味と現在分詞に由来する動詞的意味(~している、~する)が共存している。また、未来志向のto不定詞との対比で、動名詞は動作の過去的な意味を持つことができ、過去からの流れで「動作の一般的な意味」を持つこともでき、動名詞とto不定詞を目的語に持つことができる他動詞をその相性から限定的なものにする場合を生じている。
参考文献
伊関敏之 (2013) 「動名詞を中心とした世界-不定詞および現在分詞との比較を中心に-」 『人間科学研究』 第 9号 1-16 早稲田大学人間科学学術院 [編] 早稲田大学人間科学学術院
児馬修 (1996) 『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房
中尾俊夫、児馬修(編著) (1990) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館書店
大津由紀雄 (2004) 『英文法の疑問恥ずかしくてずっと聞けなかったこと』 NHK出版
(本短大教員ブログの内容は、2024年9月5日 『ASU多言語・多文化教育研究会』 愛知産業大学 での西田一弘の発表「英語「-ing形」の形態と意味の歴史的考察」を基に、加筆修正を加えたものである。) (KN)
動名詞が多様な意味体系を持っている理由を説明するのに有力な論を、伊関(2013)は動名詞と現在分詞の歴史的変遷説に基づいて、次のように述べている:
1.古英語(450~1150頃)では V-ing(動名詞)と V-ende(現在分詞)があった。
2.古英語における動名詞 V-ing は現代のそれとは大きく異なる。古英語における V-ingの特徴は現代英語における「派生名詞」とほぼ同等の性質を持っていた。
(a) John’s“refusing”the offer suddenly surprised us.(動名詞:現代英語)
※古英語においては、動名詞は直接目的語を取らなかったが、現代英語では取る。
= (b) John’s sudden“refusal”of the offer surprised us. (派生名詞:現代英語)
古英語における動名詞 V-ing は (b) の派生名詞と同様に直接目的語を取らず、副詞と共起できない名詞的な文法構造を持っていた。一方、(a) のような現代英語における動名詞 V-ing は本来、現在分詞が持つ動詞的性質に近いものである。中尾・児馬編(1990, pp. 187-188)および児馬(1996, pp. 104-108)では、以下のように説明されている。

[iŋg](ingの発音)>[in]という動名詞の音的変化と、[ind](endeの発音)>[in]という現在分詞の音的変化によって両者がほぼ同音になり、現在分詞が[iŋg]とう音とingという形態を動名詞から譲り受け、一方、動名詞は動詞句の内部構造を持つ現在分詞の統語的性質(現在分詞語尾–ende は、–ing に変わる前から、of なしで、直接、対格目的語を従えていた)を譲り受けた。対格とは直接目的語(~を)を表す言葉である。同じ語尾を持つ、現代英語の動名詞と現在分詞は、古英語の動名詞と現在分詞が、それぞれの属性の一部を交換し合った結果、生まれた現象と見なすことができる(児馬1996, p. 109)。
to不定詞のtoは「~へ」という方向を表す前置詞のtoと同じ源から発している(大津 2004)。そこで、名詞的意味(~すること)を表すto不定詞と動名詞において、to不定詞が未来志向であるのに対し、動名詞は過去志向を表す傾向が生まれるのは必然の棲み分けである。現在を表すには、to不定詞も動名詞も同様に使用されるが、動名詞には現在分詞の持つ動詞的意味「~している、~する」も含まれているので、現在志向を表す場合には動名詞が多く使用されると考えられる。(It is)nice meeting you.(会ったこと/会っていることは嬉しい。→ これからもずっとよろしく。長く話し込んだ後に述べる挨拶の言葉)
動名詞は13~14世紀に本来持っていた名詞的性質に加え、動詞的性質を持っていた現在分詞との綴りと発音の統一により、現在分詞の持っていた動詞的意味を獲得した。その為、現代英語の動名詞には古英語からの名詞的意味と現在分詞に由来する動詞的意味(~している、~する)が共存している。また、未来志向のto不定詞との対比で、動名詞は動作の過去的な意味を持つことができ、過去からの流れで「動作の一般的な意味」を持つこともでき、動名詞とto不定詞を目的語に持つことができる他動詞をその相性から限定的なものにする場合を生じている。
参考文献
伊関敏之 (2013) 「動名詞を中心とした世界-不定詞および現在分詞との比較を中心に-」 『人間科学研究』 第 9号 1-16 早稲田大学人間科学学術院 [編] 早稲田大学人間科学学術院
児馬修 (1996) 『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房
中尾俊夫、児馬修(編著) (1990) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館書店
大津由紀雄 (2004) 『英文法の疑問恥ずかしくてずっと聞けなかったこと』 NHK出版
(本短大教員ブログの内容は、2024年9月5日 『ASU多言語・多文化教育研究会』 愛知産業大学 での西田一弘の発表「英語「-ing形」の形態と意味の歴史的考察」を基に、加筆修正を加えたものである。) (KN)