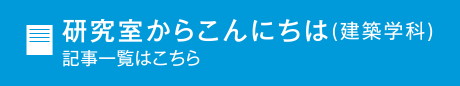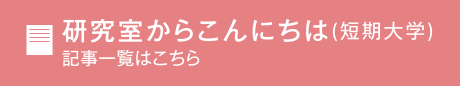哲学の難しさについて(国際コミュニケーション学科 三苫民雄)
研究室からこんにちは(短期大学)
哲学という学問は世間一般的に難しいものだという印象を持たれていると思います。
世界のあり方や人生の意義のような何か高尚かつ深遠なことが議論されているようだけれど、それを理解するためには頭が人並み外れて良くなければいけないのではないかとか思われがちです。実際私も若い頃にはそう思っていました。また、その裏返しとして、もしも哲学の本を読んでみてさっぱりわからなければ、自分が賢くないことの証明になりかねないので、まず本を手に取るところから心理的障壁があります。そして、実際に読んでみてさっぱりわからないということになると、いわゆるトラウマになりかねません。
私が大学生になって初めて読んだ哲学書はヘーゲルの『精神現象学』(樫山欽四郎訳)でしたが、数十年ぶりに引っ張り出してきた本の一節は以下のようなものです。
意識は、個々の意識が自体的には絶対的な実在であるという、自らのつかんだ思想において自己自身に帰って行く。不幸な意識にとっては、自体存在は意識自身の彼岸である。けれども、意識の動きが自分で実現したことは、個別をその完全な展開において、或は、現実の意識である個別性を、自己自身を否定するものとして、つまり対象的な極として措定したことである。(ヘーゲル『精神現象学』樫山欽四郎訳河出書房昭和48年141ページ)
私の記憶ではこれは読めたものではないと早々に投げ出したと思っていましたが、久々に本書を取り出してみて、半分までは読んでいた形跡があり、自身の我慢強さにあらためて驚かされました。実際、これは最初に読むものとしてはあまりふさわしいむものではありませんでした。しかし、その後も懲りずに哲学書を読み続け、この手の文章を読み慣れて行くと、実はそれなりにわかるようになるだけでなく、このヘーゲルも含めて哲学者によっては楽しんで読めるようになります。
ソクラテスやプラトンに始まる伝統的な西洋哲学の難しさは、おそらくこのヘーゲルにおいて頂点に達するのではないかと思われますが、少なくともヘーゲルまでの難解さはその後の20世紀のフランスのポストモダンの哲学者のそれとは大きく異なっています。後者については現代芸術の難解さと通じる別の問題があるため、また稿を改めたいと思います。今回はその伝統的哲学の難解さについて述べてみます。
しばしば最初の哲学者として名前が挙げられる古代ギリシアのソクラテス(BC469/470-399)は著作物を残しませんでした。ソクラテスの思想は弟子のプラトン(BC428/7-347/8)の、ソクラテスを主人公にした諸著作から窺い知ることができます。そのプラトンの諸著作はいわゆる「対話篇」で、ソクラテスを主人公とした演劇台本のようなスタイルとなっています。
この対話編という形式には、ソクラテスの思想をプラトンが再現した側面と、プラトンが師のソクラテスを通じて自身の思想を展開したという側面がありますが、いずれにしても真理や正義、美しさの存在と人間の善い生き方についての後の哲学の扱うべき基本的問題が考察されています。最初の哲学者は考えて話すことは好きですが本を書かない人で、2番目の哲学者は脚本家兼演出家のようなタイプでした。
哲学のスタイルが論文形式になったのは、プラトンの弟子で、「万学の祖」アリストテレス(BC384-322)からです。アリストテレスは、哲学に限らず、分析と総合に基づく科学的・体系的方法を確立しました。論文形式は客観性と説得性を保つための独特の形式が定められており、そこではソクラテスの対話での当意即妙やプラトンの演劇的センスは必要とされないどころか余計なものとして扱われかねません。他方で、そうしたソクラテスやプラトンのような特殊なセンスを持たない人でも型にはまった論述をすることはできますので、ある意味では学問は多くの人に開かれたものとなります。
こうしてひとたび学問的論文スタイルが確立すると、その分野に独特の用語が生まれてきます。たとえば、アリストテレスの「実体」という概念を「本質を含む存在」として後世の哲学者たちは共通の了解のもとに用いるようになりますが、こういう学問的用語をなんとなく曖昧なままに読んでしまうと、わからないことが雪だるま的に増えてしまいます。ということは、特殊概念や用語の理解をおろそかにせず、どのような問題が受け継がれていったかということを見ていけば、先哲の諸著作は無機質な概念の羅列ではなくなります。どのような問題が代々考えられてきたかということがわかれば、それぞれの哲学者たちが、様々な意匠を凝らしながら問題に接近している姿も見えてきます。
哲学が本に書かれるものとなってくると、それは芸術に近づいていきます。例えば、クラシックの交響曲などは、それを聴き慣れないうちは、そもそもどの楽器が何の音を出しているかもわからず、私などは子どもの頃はひたすら退屈していました。それが西洋古典音楽と交響曲の形式に次第に馴染んでくると、指揮者や交響楽団の違いも自ずとわかるようになってきます。フルトヴェングラー指揮のマーラー5番は最高だとか、弦楽器はウィーン・フィルだけど、金管はフィラデルフィア交響楽団だよね、などと一端に通ぶってみたりする学生はきっと今もそれなりにいることでしょう。
西洋哲学の難しさもこれと似たところがあり、通ぶってみる必要はありませんが、哲学的意匠には慣れることができますし、その違いもわかるようになります。ただ、西洋哲学の表現上の難しさが使用される概念や用語の問題に集約されるなら、概念や用語について順を追って丁寧に学んでいけば、文章は論文として論理的に書かれてはいるので、理解できるはずです。実際に大学の哲学の講義ではそういう内容が講義されるのが普通です。
ただ、ここで本来なら理解できるにもかかわらず、理解を妨げるもう一つの問題があります。それは哲学者たちが前提としている世界観の問題です。すなわち、世界にはあらゆるものの原因となって、世界を支配している超越的で絶対的な存在があるということです。中世のキリスト教哲学においては神の存在は当然のことですが、キリスト教以前の古代ギリシアのソクラテス、プラトン、アリストテレスの3者ともに、この絶対者の存在については揺るぎなき信仰がありました。デカルト(1596-1650)以降の近代哲学者においてもこの点に関する事情は同じで、むしろ近代哲学はキリスト教の聖書の記述の注釈のように見えるところもあります。
旧約聖書「出エジプト記」(3.7.-14)において、モーゼが神にその名前を尋ねたところ、「わたしはある」という神だと答えます。デカルトはその根拠付けを「私は考える、だから私はある」と「私は考える」=理性に基づいて、神の概念を用いずに出発できる近代合理主義を建てることになりますが、この有名な命題の直前の考察で、この考える「私」を創造したのは神であることが前提にされています。このこと自体キリスト教文化圏においては誰も違和感なく受け入れる前提ですが、ここをわかったような顔をして通り過ぎてしまうと、その後の近代哲学の流れもつかめなくなりかねません。その後のカントもヘーゲルも熱烈なクリスチャンだったということを抜きにしては語れないのですが、東洋の東端の島国の異文化の住民にはこれが躓きの石になってきました。
というわけで、ヘーゲルに至るまでの哲学の難しさはおよそこの2点に原因があると思われます。ただし、この難しさを克服することはそれなりに教養としての西洋近代哲学を理解するには役立ちますし、これをうまく理解できると、難解と言われるヘーゲル哲学もマーラーの交響曲のように楽しむことができるようになります。
もちろん、それはそれでいいのですが、こうした学問的知識を他人に対してひけらかしてみたり、そのことでマウントを取ろうとしたりするようになると、哲学の本来の目的を見失ってしまいます。哲学の意匠はあくまで意匠にしか過ぎません。たとえて言えば、これは音楽の一部のジャンルに通じているだけで、クラシックはわかるけれど他のジャンルの音楽はわからないとかいう話になります。また、ジャンルにこだわるうちに、どうかするとしばしば音楽自体を楽しむことが忘れられがちになります。
哲学の目的は、ソクラテスが言っていたように「善く生きる」ことです。この世において真善美を追求するために、よく考え、よく学び、そして善く生きることが本来の哲学的営みです。この基本を外れないように心しながら、先人の哲学を楽しんでいただけたら幸いです。
世界のあり方や人生の意義のような何か高尚かつ深遠なことが議論されているようだけれど、それを理解するためには頭が人並み外れて良くなければいけないのではないかとか思われがちです。実際私も若い頃にはそう思っていました。また、その裏返しとして、もしも哲学の本を読んでみてさっぱりわからなければ、自分が賢くないことの証明になりかねないので、まず本を手に取るところから心理的障壁があります。そして、実際に読んでみてさっぱりわからないということになると、いわゆるトラウマになりかねません。
私が大学生になって初めて読んだ哲学書はヘーゲルの『精神現象学』(樫山欽四郎訳)でしたが、数十年ぶりに引っ張り出してきた本の一節は以下のようなものです。
意識は、個々の意識が自体的には絶対的な実在であるという、自らのつかんだ思想において自己自身に帰って行く。不幸な意識にとっては、自体存在は意識自身の彼岸である。けれども、意識の動きが自分で実現したことは、個別をその完全な展開において、或は、現実の意識である個別性を、自己自身を否定するものとして、つまり対象的な極として措定したことである。(ヘーゲル『精神現象学』樫山欽四郎訳河出書房昭和48年141ページ)
私の記憶ではこれは読めたものではないと早々に投げ出したと思っていましたが、久々に本書を取り出してみて、半分までは読んでいた形跡があり、自身の我慢強さにあらためて驚かされました。実際、これは最初に読むものとしてはあまりふさわしいむものではありませんでした。しかし、その後も懲りずに哲学書を読み続け、この手の文章を読み慣れて行くと、実はそれなりにわかるようになるだけでなく、このヘーゲルも含めて哲学者によっては楽しんで読めるようになります。
ソクラテスやプラトンに始まる伝統的な西洋哲学の難しさは、おそらくこのヘーゲルにおいて頂点に達するのではないかと思われますが、少なくともヘーゲルまでの難解さはその後の20世紀のフランスのポストモダンの哲学者のそれとは大きく異なっています。後者については現代芸術の難解さと通じる別の問題があるため、また稿を改めたいと思います。今回はその伝統的哲学の難解さについて述べてみます。
しばしば最初の哲学者として名前が挙げられる古代ギリシアのソクラテス(BC469/470-399)は著作物を残しませんでした。ソクラテスの思想は弟子のプラトン(BC428/7-347/8)の、ソクラテスを主人公にした諸著作から窺い知ることができます。そのプラトンの諸著作はいわゆる「対話篇」で、ソクラテスを主人公とした演劇台本のようなスタイルとなっています。
この対話編という形式には、ソクラテスの思想をプラトンが再現した側面と、プラトンが師のソクラテスを通じて自身の思想を展開したという側面がありますが、いずれにしても真理や正義、美しさの存在と人間の善い生き方についての後の哲学の扱うべき基本的問題が考察されています。最初の哲学者は考えて話すことは好きですが本を書かない人で、2番目の哲学者は脚本家兼演出家のようなタイプでした。
哲学のスタイルが論文形式になったのは、プラトンの弟子で、「万学の祖」アリストテレス(BC384-322)からです。アリストテレスは、哲学に限らず、分析と総合に基づく科学的・体系的方法を確立しました。論文形式は客観性と説得性を保つための独特の形式が定められており、そこではソクラテスの対話での当意即妙やプラトンの演劇的センスは必要とされないどころか余計なものとして扱われかねません。他方で、そうしたソクラテスやプラトンのような特殊なセンスを持たない人でも型にはまった論述をすることはできますので、ある意味では学問は多くの人に開かれたものとなります。
こうしてひとたび学問的論文スタイルが確立すると、その分野に独特の用語が生まれてきます。たとえば、アリストテレスの「実体」という概念を「本質を含む存在」として後世の哲学者たちは共通の了解のもとに用いるようになりますが、こういう学問的用語をなんとなく曖昧なままに読んでしまうと、わからないことが雪だるま的に増えてしまいます。ということは、特殊概念や用語の理解をおろそかにせず、どのような問題が受け継がれていったかということを見ていけば、先哲の諸著作は無機質な概念の羅列ではなくなります。どのような問題が代々考えられてきたかということがわかれば、それぞれの哲学者たちが、様々な意匠を凝らしながら問題に接近している姿も見えてきます。
哲学が本に書かれるものとなってくると、それは芸術に近づいていきます。例えば、クラシックの交響曲などは、それを聴き慣れないうちは、そもそもどの楽器が何の音を出しているかもわからず、私などは子どもの頃はひたすら退屈していました。それが西洋古典音楽と交響曲の形式に次第に馴染んでくると、指揮者や交響楽団の違いも自ずとわかるようになってきます。フルトヴェングラー指揮のマーラー5番は最高だとか、弦楽器はウィーン・フィルだけど、金管はフィラデルフィア交響楽団だよね、などと一端に通ぶってみたりする学生はきっと今もそれなりにいることでしょう。
西洋哲学の難しさもこれと似たところがあり、通ぶってみる必要はありませんが、哲学的意匠には慣れることができますし、その違いもわかるようになります。ただ、西洋哲学の表現上の難しさが使用される概念や用語の問題に集約されるなら、概念や用語について順を追って丁寧に学んでいけば、文章は論文として論理的に書かれてはいるので、理解できるはずです。実際に大学の哲学の講義ではそういう内容が講義されるのが普通です。
ただ、ここで本来なら理解できるにもかかわらず、理解を妨げるもう一つの問題があります。それは哲学者たちが前提としている世界観の問題です。すなわち、世界にはあらゆるものの原因となって、世界を支配している超越的で絶対的な存在があるということです。中世のキリスト教哲学においては神の存在は当然のことですが、キリスト教以前の古代ギリシアのソクラテス、プラトン、アリストテレスの3者ともに、この絶対者の存在については揺るぎなき信仰がありました。デカルト(1596-1650)以降の近代哲学者においてもこの点に関する事情は同じで、むしろ近代哲学はキリスト教の聖書の記述の注釈のように見えるところもあります。
旧約聖書「出エジプト記」(3.7.-14)において、モーゼが神にその名前を尋ねたところ、「わたしはある」という神だと答えます。デカルトはその根拠付けを「私は考える、だから私はある」と「私は考える」=理性に基づいて、神の概念を用いずに出発できる近代合理主義を建てることになりますが、この有名な命題の直前の考察で、この考える「私」を創造したのは神であることが前提にされています。このこと自体キリスト教文化圏においては誰も違和感なく受け入れる前提ですが、ここをわかったような顔をして通り過ぎてしまうと、その後の近代哲学の流れもつかめなくなりかねません。その後のカントもヘーゲルも熱烈なクリスチャンだったということを抜きにしては語れないのですが、東洋の東端の島国の異文化の住民にはこれが躓きの石になってきました。
というわけで、ヘーゲルに至るまでの哲学の難しさはおよそこの2点に原因があると思われます。ただし、この難しさを克服することはそれなりに教養としての西洋近代哲学を理解するには役立ちますし、これをうまく理解できると、難解と言われるヘーゲル哲学もマーラーの交響曲のように楽しむことができるようになります。
もちろん、それはそれでいいのですが、こうした学問的知識を他人に対してひけらかしてみたり、そのことでマウントを取ろうとしたりするようになると、哲学の本来の目的を見失ってしまいます。哲学の意匠はあくまで意匠にしか過ぎません。たとえて言えば、これは音楽の一部のジャンルに通じているだけで、クラシックはわかるけれど他のジャンルの音楽はわからないとかいう話になります。また、ジャンルにこだわるうちに、どうかするとしばしば音楽自体を楽しむことが忘れられがちになります。
哲学の目的は、ソクラテスが言っていたように「善く生きる」ことです。この世において真善美を追求するために、よく考え、よく学び、そして善く生きることが本来の哲学的営みです。この基本を外れないように心しながら、先人の哲学を楽しんでいただけたら幸いです。