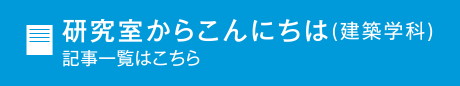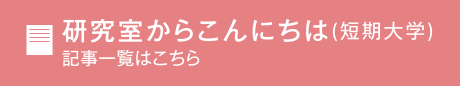法学への多角的アプローチについて(国際コミュニケーション学科 三苫民雄)
研究室からこんにちは(短期大学)
以下は、友人の研究者の著書(スモディシュ・イェネー著『学際的、文化的そして世界的脈絡における法、法的価値および国家』2019)に寄せた序文で、そのうち、法学と哲学と歴史学のあるべき関係について論じた箇所を抜粋して掲載します。研究報告の一種と思っていただければ幸いです。
*
法律家や法学者は法を解釈する。法治国家における官僚もまた法治行政原理に基づいて行政行為を行うことになっている。われわれの日常生活における出来事も、ときには法的紛争として裁判所の判断を仰ぐことがある。そして、法的手続きを経た正義は社会において強制力を伴う政治権力となる。
法律学は昔から「パンのための学問」と言われてきたが、実際、現役の法律家や官僚(そしてその志望者)にとっては、文字どおり飯のタネである。
一般に法律学は大学の法学部で教えられているが、そこでのカリキュラムの中心となっているのは、いわゆる法律解釈学である。法律条文の意味を現実の法的紛争との関わりの中で明らかにしていく法律解釈学は、実際かなり特殊専門的な技術であり、条文の字義通りの解釈にとどまらない。法律は物理的にすべての社会事象を条文化できるはずはなく、またその必要もないため、条文が行き届かない点については、法律家は立法者の意図や、類推論理、禁反言の法理、公序良俗といった独特の論理や道徳規範を総動員して意味を特定していくことになる。この法律解釈学の技法はローマ法時代(あるいはそれにさかのぼる古代ローマの十二表法(BC450)の時代)以来、法律家たちに受け継がれてきたとも言えるかもしれない。黒を白と言いくるめるようなところのあるこの解釈技法は、社会通念的にはあまり評判はよろしくないように見える一方で、西洋社会においては、社会に新たな価値基準を提示するという肯定的な評価もなされてきた。わが国では想像し難い西洋社会における法律家に対する社会的信頼と高評価は、この法解釈学の創造性に由来する。
とはいうものの、法律学の論理は、実はそれほど込み入ったものではない。法律解釈の技法を仔細に分析してみると、その論理と修辞は最終的に訴訟当事者の利害調整、社会的文化的諸価値の比較衡量に行き着くように見える。
この伝統的法解釈技術は近代市民社会にとって必要不可欠なものではあるが、その長所の裏返しとして、それは二つの弱点を抱えている。
その一つはこの法解釈体系の中にとどまる限り、われわれは正義の根底が何なのかを示すことができないということである。人類史を振り返ると、正義は神々、そして唯一神、後に神の代理人としての絶対君主に由来するという明確な根拠を持っていたが、近代市民社会においては、神も王も排除されたため「法はそれが法であるがゆえに正しい」という自己同一的な命題が意義を持つものとなった。それはそれで意義深いものではあるものの、わかりやすい正義の根拠を求める人にとっては、この命題は屁理屈にしか見えないだろう。
法律解釈学のもうひとつの弱点は「法とは何か」という問いに答えられないことである。法律解釈学は法律条文と現実の問題との間の接合を図り、それに兎にも角にも成功してきたように見える。それは語学習得のための文法と実際の用法との関係にも似たところがある。そして、いくら精緻に作り上げた体系であっても、文法そのものをもって言語だと言うことはできない。法律解釈学もまた大変有益な技法ではあるものの、法それ自体ではない。
法解釈学のこうした弱点は、立法や政策のように法制度全体が対象になる場合に如実に現れてくる。われわれが将来新たな法制度を設計しようとするなら、法解釈学は正義と法について根本的に考えるための哲学すなわち法哲学と、過去の法制度を振り返ることのできる歴史学すなわち法制史の協力を得なければならないだろう。
*
法律家や法学者は法を解釈する。法治国家における官僚もまた法治行政原理に基づいて行政行為を行うことになっている。われわれの日常生活における出来事も、ときには法的紛争として裁判所の判断を仰ぐことがある。そして、法的手続きを経た正義は社会において強制力を伴う政治権力となる。
法律学は昔から「パンのための学問」と言われてきたが、実際、現役の法律家や官僚(そしてその志望者)にとっては、文字どおり飯のタネである。
一般に法律学は大学の法学部で教えられているが、そこでのカリキュラムの中心となっているのは、いわゆる法律解釈学である。法律条文の意味を現実の法的紛争との関わりの中で明らかにしていく法律解釈学は、実際かなり特殊専門的な技術であり、条文の字義通りの解釈にとどまらない。法律は物理的にすべての社会事象を条文化できるはずはなく、またその必要もないため、条文が行き届かない点については、法律家は立法者の意図や、類推論理、禁反言の法理、公序良俗といった独特の論理や道徳規範を総動員して意味を特定していくことになる。この法律解釈学の技法はローマ法時代(あるいはそれにさかのぼる古代ローマの十二表法(BC450)の時代)以来、法律家たちに受け継がれてきたとも言えるかもしれない。黒を白と言いくるめるようなところのあるこの解釈技法は、社会通念的にはあまり評判はよろしくないように見える一方で、西洋社会においては、社会に新たな価値基準を提示するという肯定的な評価もなされてきた。わが国では想像し難い西洋社会における法律家に対する社会的信頼と高評価は、この法解釈学の創造性に由来する。
とはいうものの、法律学の論理は、実はそれほど込み入ったものではない。法律解釈の技法を仔細に分析してみると、その論理と修辞は最終的に訴訟当事者の利害調整、社会的文化的諸価値の比較衡量に行き着くように見える。
この伝統的法解釈技術は近代市民社会にとって必要不可欠なものではあるが、その長所の裏返しとして、それは二つの弱点を抱えている。
その一つはこの法解釈体系の中にとどまる限り、われわれは正義の根底が何なのかを示すことができないということである。人類史を振り返ると、正義は神々、そして唯一神、後に神の代理人としての絶対君主に由来するという明確な根拠を持っていたが、近代市民社会においては、神も王も排除されたため「法はそれが法であるがゆえに正しい」という自己同一的な命題が意義を持つものとなった。それはそれで意義深いものではあるものの、わかりやすい正義の根拠を求める人にとっては、この命題は屁理屈にしか見えないだろう。
法律解釈学のもうひとつの弱点は「法とは何か」という問いに答えられないことである。法律解釈学は法律条文と現実の問題との間の接合を図り、それに兎にも角にも成功してきたように見える。それは語学習得のための文法と実際の用法との関係にも似たところがある。そして、いくら精緻に作り上げた体系であっても、文法そのものをもって言語だと言うことはできない。法律解釈学もまた大変有益な技法ではあるものの、法それ自体ではない。
法解釈学のこうした弱点は、立法や政策のように法制度全体が対象になる場合に如実に現れてくる。われわれが将来新たな法制度を設計しようとするなら、法解釈学は正義と法について根本的に考えるための哲学すなわち法哲学と、過去の法制度を振り返ることのできる歴史学すなわち法制史の協力を得なければならないだろう。