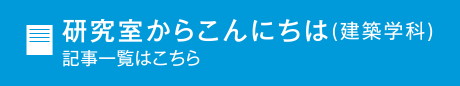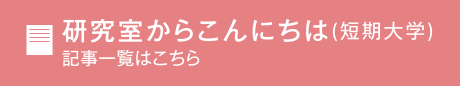哲学の面白さについて(国際コミュニケーション学科 三苫民雄)
研究室からこんにちは(短期大学)
先に私の担当回で述べた「哲学の難しさについて」には、実はもう少し続きがあります。
西洋哲学の難しさは学問的な論文形式の問題と唯一絶対神の問題に原因があると述べましたが、この2つの問題は人びとが信仰から離れるにつれて、新たな様相を呈してきます。
人びとが神の観念を背後に押しやり、人間の理性だけで哲学を語ろうとし始めてからも、神は長らく理性の後ろ盾となって哲学者を支えて来ましたし、デカルトもカントもヘーゲルも実際その著作からも明らかに熱烈と言えるほどのキリスト信徒です。ところが、その熱烈な信仰にもかかわらず、彼らが哲学的に思考することによって神から離れていってしまうということが生じてきます。
一般にデカルトに始まるとされる近代哲学ですが、それ以前の哲学からその後のヘーゲルに至るまで、哲学は他の学問と同様に、世界の法則を発見し、神を賛美すると言う意図のもとに進められてきました。すでに中世において、人間の本性を人間的自然として、その自然法則を発見しようとするトマス・アクィナスの示した姿勢は、17世紀のベーコンやデカルトにおいても継承され、人間の本性を理性、すなわち、人間の中にある合理性を追求しようとしてきました。
合理性そのものは一見したところそれだけで成り立つように思われます。あるものが存在する場合に、そのあるものAについて「AはAである」という論理を立てること、一度そう断じられてしまえば、その正しさは疑いをえない盤石なものに見えます。ただ、これをデカルトがそうしたように、ひとたび疑い始めると、すべてが疑わしいものになってしまいます。
デカルトの場合はあらゆるものが確実に存在するのかということを考え抜いた末に、そもそもそんな厄介なことを「考える私」は打ち消しえないという結論に至ります。この「考える私」という理性が、その後の哲学、そして科学の正しさの根拠となります。デカルト本人は考える「私」を成り立たせている根拠は神であると、著書『方法序説』の中の有名な「私は考える、だから私はある」という表現が出てくる数段落前に明言しています。しかし、その後の哲学そして科学は、デカルトの立論の根拠ではなく結論である「理性」を新たな出発点として議論を組み立てるという方向に進んでいきます。
このときから、それまで神を根拠にしていた理性は、ただ理性それだけで正しいものとして追求されていくのですが、それだけを抜き取ってみるとやはり正しさの根拠は見いだせないことがわかります。実際、理性というものはその出発点で方向を間違うと、理路整然と自らを展開しながらとんでもない結論を導き出しますし、目的を見誤っても、その誤った目的に向かって、これまた理路整然と自らを展開します。しかし、近代科学は哲学の結論を出発点として、実際にその後は神様なしでややこしいことを考えずに実験観察を重ねつつ、発展を遂げてきました。
その一方、本家の哲学の方ではデカルトの方向で理性を追求してみると、実は様々な不具合が出てくることわかってきます。理性だけで哲学を構成するのは無理があるため、理性ではなく経験の上に哲学を組み立てようとしたり(イギリス経験論)、アリストテレス以来の形而上学の流れで再度神様を召喚したり(大陸合理論)するのですが、このとき理性の中に神にとって代わる正しさを組み込んで世界をすべて説明する壮大な哲学体系を作り上げたのがヘーゲルでした。
ヘーゲル本人が熱烈なキリスト信徒であったことは先にも述べましたが、彼の哲学もまた極めてキリスト教的な特徴を持っています。ヘーゲルは理性を単なる形式論理的な思考とは考えず、理性の中に神の存在を組み込んで、神の栄光を讃えるべき人間存在のあり方についていわば壮大な物語を仕立て上げました。
ヘーゲルが理性に独特の意味をもたせることができたのは、彼の用いた論理が独特のものだったからです。いわゆる弁証法論理というのがそれです。「AはAである」という論理は、AはいつまでもAであるわけはなく、時の流れの中でAのままではいられなくなる上に、AではないものやAと対立するものとの関わりの中で、何か新たなものへと 発展するという論理です。
これはそれまでの形式論理の前提となっている「AはAである」とは根本的に異なる論理になっています。弁証法では「AはAである」という論理は一旦成立しても、論理に時間という要素を組み入れることで「AはAでないものになりうる」ことを示しているからです。形式論理に時間という歴史の要素を組み込むことでA自らがAでないものとなるだけでなく、Aとは異質の存在との関わりの中で、自身が異次元の存在に上昇するという物語が出来上がります。
弁証法はそれまでの論理からすると、いわば何でもありにすら見えます。というのは「Aでないもの」は世界に無数にあり、そのどれを選ぶのかということは論者次第だからです。ヘーゲル自身はこの論理を駆使して世界と存在のすべてを語り尽くすような壮大な物語を描くことになります。
ところがここで問題が生じます。この弁証法論理の全体はヘーゲル自身のキリスト教的世界観と軌を一にするものですが、本人の熱烈な信仰にもかかわらず、弁証法論理それ自体には「AはAである」というそれまでの形式論理の背景にある神様を冒涜しかねない要素が含まれています。冒涜ということではなくても、この弁証法論理は、結果として神の存在がなくても人間の理性だけで世界は成立し、発展していく体系となっています。
元々弁証法はソクラテスが実践していた、対話を通じて真理を発見するといういわば「産婆術」に由来します。これを活写したのがプラトンの対話篇ですが、この意味で、弁証法論理はもともと哲学にとっては馴染深い論理でしたし、ヘーゲルはそこに新たな生命を吹き込んだと言ってもいいでしょう。ヘーゲル自身の書いた文章は難解ですが、同時に比類なき面白さを獲得しています。一旦これに気がつくとやみつきになるほどです。
ただ、ヘーゲルが本人の意図に反して、その哲学的論理が神から離れてしまったことは、のちの人びとへの置き土産として大いなる「不安」を残してしまいます。ヘーゲル本人には揺るぎなき信仰があったからいいのですが、唯一絶対神への信仰もなく、ヘーゲルの絶対理念とかいった概念に全幅の信頼を寄せるわけにもいかない後世の人びとにとっては、この神から見放された人びとの「不安」の解消が次の課題となります。
というわけで、こうしたヘーゲルの後を受けて、ニーチェ、キルケゴール、マルクスはそれぞれ三者三様にこの問題に答えようとしたのですが、今回は話が長くなりましたので、ここで一旦筆を置くことにします。
西洋哲学の難しさは学問的な論文形式の問題と唯一絶対神の問題に原因があると述べましたが、この2つの問題は人びとが信仰から離れるにつれて、新たな様相を呈してきます。
人びとが神の観念を背後に押しやり、人間の理性だけで哲学を語ろうとし始めてからも、神は長らく理性の後ろ盾となって哲学者を支えて来ましたし、デカルトもカントもヘーゲルも実際その著作からも明らかに熱烈と言えるほどのキリスト信徒です。ところが、その熱烈な信仰にもかかわらず、彼らが哲学的に思考することによって神から離れていってしまうということが生じてきます。
一般にデカルトに始まるとされる近代哲学ですが、それ以前の哲学からその後のヘーゲルに至るまで、哲学は他の学問と同様に、世界の法則を発見し、神を賛美すると言う意図のもとに進められてきました。すでに中世において、人間の本性を人間的自然として、その自然法則を発見しようとするトマス・アクィナスの示した姿勢は、17世紀のベーコンやデカルトにおいても継承され、人間の本性を理性、すなわち、人間の中にある合理性を追求しようとしてきました。
合理性そのものは一見したところそれだけで成り立つように思われます。あるものが存在する場合に、そのあるものAについて「AはAである」という論理を立てること、一度そう断じられてしまえば、その正しさは疑いをえない盤石なものに見えます。ただ、これをデカルトがそうしたように、ひとたび疑い始めると、すべてが疑わしいものになってしまいます。
デカルトの場合はあらゆるものが確実に存在するのかということを考え抜いた末に、そもそもそんな厄介なことを「考える私」は打ち消しえないという結論に至ります。この「考える私」という理性が、その後の哲学、そして科学の正しさの根拠となります。デカルト本人は考える「私」を成り立たせている根拠は神であると、著書『方法序説』の中の有名な「私は考える、だから私はある」という表現が出てくる数段落前に明言しています。しかし、その後の哲学そして科学は、デカルトの立論の根拠ではなく結論である「理性」を新たな出発点として議論を組み立てるという方向に進んでいきます。
このときから、それまで神を根拠にしていた理性は、ただ理性それだけで正しいものとして追求されていくのですが、それだけを抜き取ってみるとやはり正しさの根拠は見いだせないことがわかります。実際、理性というものはその出発点で方向を間違うと、理路整然と自らを展開しながらとんでもない結論を導き出しますし、目的を見誤っても、その誤った目的に向かって、これまた理路整然と自らを展開します。しかし、近代科学は哲学の結論を出発点として、実際にその後は神様なしでややこしいことを考えずに実験観察を重ねつつ、発展を遂げてきました。
その一方、本家の哲学の方ではデカルトの方向で理性を追求してみると、実は様々な不具合が出てくることわかってきます。理性だけで哲学を構成するのは無理があるため、理性ではなく経験の上に哲学を組み立てようとしたり(イギリス経験論)、アリストテレス以来の形而上学の流れで再度神様を召喚したり(大陸合理論)するのですが、このとき理性の中に神にとって代わる正しさを組み込んで世界をすべて説明する壮大な哲学体系を作り上げたのがヘーゲルでした。
ヘーゲル本人が熱烈なキリスト信徒であったことは先にも述べましたが、彼の哲学もまた極めてキリスト教的な特徴を持っています。ヘーゲルは理性を単なる形式論理的な思考とは考えず、理性の中に神の存在を組み込んで、神の栄光を讃えるべき人間存在のあり方についていわば壮大な物語を仕立て上げました。
ヘーゲルが理性に独特の意味をもたせることができたのは、彼の用いた論理が独特のものだったからです。いわゆる弁証法論理というのがそれです。「AはAである」という論理は、AはいつまでもAであるわけはなく、時の流れの中でAのままではいられなくなる上に、AではないものやAと対立するものとの関わりの中で、何か新たなものへと 発展するという論理です。
これはそれまでの形式論理の前提となっている「AはAである」とは根本的に異なる論理になっています。弁証法では「AはAである」という論理は一旦成立しても、論理に時間という要素を組み入れることで「AはAでないものになりうる」ことを示しているからです。形式論理に時間という歴史の要素を組み込むことでA自らがAでないものとなるだけでなく、Aとは異質の存在との関わりの中で、自身が異次元の存在に上昇するという物語が出来上がります。
弁証法はそれまでの論理からすると、いわば何でもありにすら見えます。というのは「Aでないもの」は世界に無数にあり、そのどれを選ぶのかということは論者次第だからです。ヘーゲル自身はこの論理を駆使して世界と存在のすべてを語り尽くすような壮大な物語を描くことになります。
ところがここで問題が生じます。この弁証法論理の全体はヘーゲル自身のキリスト教的世界観と軌を一にするものですが、本人の熱烈な信仰にもかかわらず、弁証法論理それ自体には「AはAである」というそれまでの形式論理の背景にある神様を冒涜しかねない要素が含まれています。冒涜ということではなくても、この弁証法論理は、結果として神の存在がなくても人間の理性だけで世界は成立し、発展していく体系となっています。
元々弁証法はソクラテスが実践していた、対話を通じて真理を発見するといういわば「産婆術」に由来します。これを活写したのがプラトンの対話篇ですが、この意味で、弁証法論理はもともと哲学にとっては馴染深い論理でしたし、ヘーゲルはそこに新たな生命を吹き込んだと言ってもいいでしょう。ヘーゲル自身の書いた文章は難解ですが、同時に比類なき面白さを獲得しています。一旦これに気がつくとやみつきになるほどです。
ただ、ヘーゲルが本人の意図に反して、その哲学的論理が神から離れてしまったことは、のちの人びとへの置き土産として大いなる「不安」を残してしまいます。ヘーゲル本人には揺るぎなき信仰があったからいいのですが、唯一絶対神への信仰もなく、ヘーゲルの絶対理念とかいった概念に全幅の信頼を寄せるわけにもいかない後世の人びとにとっては、この神から見放された人びとの「不安」の解消が次の課題となります。
というわけで、こうしたヘーゲルの後を受けて、ニーチェ、キルケゴール、マルクスはそれぞれ三者三様にこの問題に答えようとしたのですが、今回は話が長くなりましたので、ここで一旦筆を置くことにします。